はじまりは、「裏切り」から
アフリカのケニアに行ってきました。
今回は、遠回りになりますが、往復ともにパリ経由でケニアに行きました。
その様子を報告します。
初めてのアフリカ。
灼熱の大地を想像していました。
しかし、日本からパリを経由し、長いフライトの末に降り立ったケニアの首都ナイロビのジョモ・ケニヤッタ国際空港に降り立つと、その空気は、私の予想を心地よく裏切ってくれました。
到着は夜でしたが、ケニアの夜は涼しく、むしろ少し寒いくらいでした。
日中も空気が涼しく、乾いていて、爽やかで、まるで日本の軽井沢のようです。
ナイロビは標高1600メートルを超える高地に位置する都市です。
日本のうだるような夏とは全く違う、過ごしやすい気候がそこにはありました。
年間を通じても最高気温が30℃を超えることは稀で、日本の方がよほど灼熱といえます。
ケニアに滞在した9月は日本では残暑が厳しい時期ですが、ケニアでは夜が日中でも最高気温が25℃前後、朝晩は15℃くらいまで下がります。
この最初の「裏切り」は、今回私の数々の固定観念が覆される出来事のほんの始まりに過ぎませんでした。
今回私がケニアを訪れた理由・経緯はいろいろとあるのですが、個人的にも強い興味がありました。
私は日本弁護士連合会や大阪弁護士会で都市環境を研究する委員会に所属しています。
そこでは都市の環境に関するさまざまな研究を行っています。
そのような経験から、今まさに急成長を遂げているアフリカの都市がどのような姿をしているのか、この目で確かめてみたいと思っていました。
高速道路を走る車の窓からはキリンの姿が悠然と疾走
ケニアは東アフリカ地域の経済的中心地としての地位を確立しています。
域内最大のGDPを誇り、内陸国への玄関口であるモンバサ港を擁することで、地域経済において不可欠な役割を担っています。
そんなケニアの首都ナイロビの日常に、非日常が突然飛び込んできたのは、高速道路を走っている時でした。
ふと窓の外に目をやると、遠くに野生のキリンが悠然と走っていました。

アフリカのサファリといえば、都市から遠く離れた大自然の中にあるのが一般的です。
しかし、ナイロビは世界でも非常に珍しい、首都のすぐ隣に国立公園が広がる都市です。
日本車と黒い煙に包まれた街
首都ナイロビの街は、一言でいえば「エネルギーの塊」でした。街には活気があふれ、人々はエネルギッシュ。
そして、ものすごい数の車が道を埋め尽くしています。
驚いたのはその車の多くが日本車だったことです。

ケニアは日本と同じ左側通行・右ハンドル。
そのため、丈夫で信頼性の高い日本の中古車が絶大な人気を誇っているそうです。
街中で見慣れた日本のメーカーの車が走っているのを見ると、遠いアフリカの地で日本の技術が人々の生活を支えていることを実感しました。
しかし、その活気の裏側で、深刻な問題も目の当たりにしました。
交通量の多さからくる排気ガスです。
それは「空気が悪い」というレベルではなく、目に見えるほどの黒い煙がもうもうと立ち上り、健康への影響を心配せずにはいられない光景でした。
写真ではあまり見えませんが、白い煙や黒い煙の中にずっといるような感じでした。
ケニアでは人口増加、自動車登録台数の増加、非効率的で分断された道路網が渋滞を引き起こすと同時に、大気汚染を生じさせており、以下のような報告があります。
「世界保健機関(WHO)は、ケニアでは年間約19,000人が大気汚染により死亡していると推定しています。国連環境計画(UNEP)は、ナイロビの大気汚染レベルが推奨基準値の70%に達していると報告しています。さらに、2,000万人のケニア人が、大気質の悪化によって呼吸器疾患を患っていると推定されています。これらの症状は、特に車両の排気ガスによって悪化しており、車両の排気ガスは大気汚染の大きな原因となっています。」
日本では1970年代頃から自動車の排ガスが公害として社会問題となりました。
(関西では、国道43号線公害訴訟(1976-)、西淀川公害訴訟(1978-)、尼崎公害訴訟(1988-)などが有名です。当時の状況を知らなかったため具体的なイメージを持つことが出来なかった面がありましたが、今回のケニア滞在を通じて排気ガスの問題を少しは実感することができました。)
この問題に対処するため、日本の国際協力機構(JICA)をはじめとする国際社会が支援に乗り出しています。
ケニア政府が「ナイロビ都市開発マスタープラン」(戦略的マスタープランの一環)の中でも優先プロジェクトとして挙げていたナイロビ駅付近の操車場を跨ぐ高架橋の建設や道路の拡幅といったプロジェクトは、日本の円借款を活用して進められており、日・ケニア間の協力関係を象徴する事業となっています。
ケニアで出会った日本の日常
驚いたのは、ケニアで暮らす日本人の多さです。
在ケニア日本大使館の安全の手引きによると、2025年2月時点で800人を超える日本人がいるそうです。
私が滞在していた建物にも、多くの日本人家族が住んでいました。
廊下に出ると、日本人の子どもたちが元気に走り回っていたり、日本人女性が井戸端会議をしていて、その光景は、まるで日本にいるかのような錯覚を覚えるほどでした。
しかし、ここが日本でないことを思い出させる現実もあります。
その建物の入り口は、24時間、機関銃を持った警備員によって固く守られています。
外務省の海外安全情報を見ても、ナイロビでは「昼夜を問わず徒歩での移動を避ける」よう勧告されています。
私も道を挟んだ徒歩数分程度の場所への移動も徒歩は避け、車で移動していました。
滞在中、JICA(国際協力機構)のオフィスにも行きました。

JICAが入るビルの窓からはナイロビのオフィス街、そして日本大使館の建物も見えました。

日本大使館を訪れる機会もありました。
大使館中の広報文化センター(JICC)には日本文化を紹介するための図書室があり、日本の貴重な書籍が並んでいます。
日本の漫画も収録されており、その中には私の大好きな漫画 八木教広作『CLAYMORE』(クレイモア)<2001-2014>の英語版が置いてありました。
ケニアの日本大使館で、自分の好きな作品に再会することができて大変嬉しく思いました。
(なお、『CLAYMORE』については、2025年3月12日、アメリカで実写ドラマ化の企画が進行中であると地元オンラインマガジン「DEADLINE」が報じています。)
<つづく>次回は、アフリカ最大のスラムとも言われる「キベラスラム」について
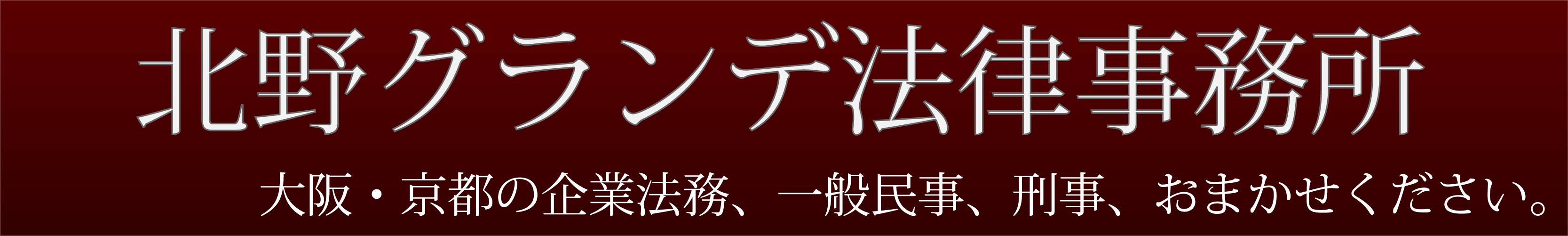



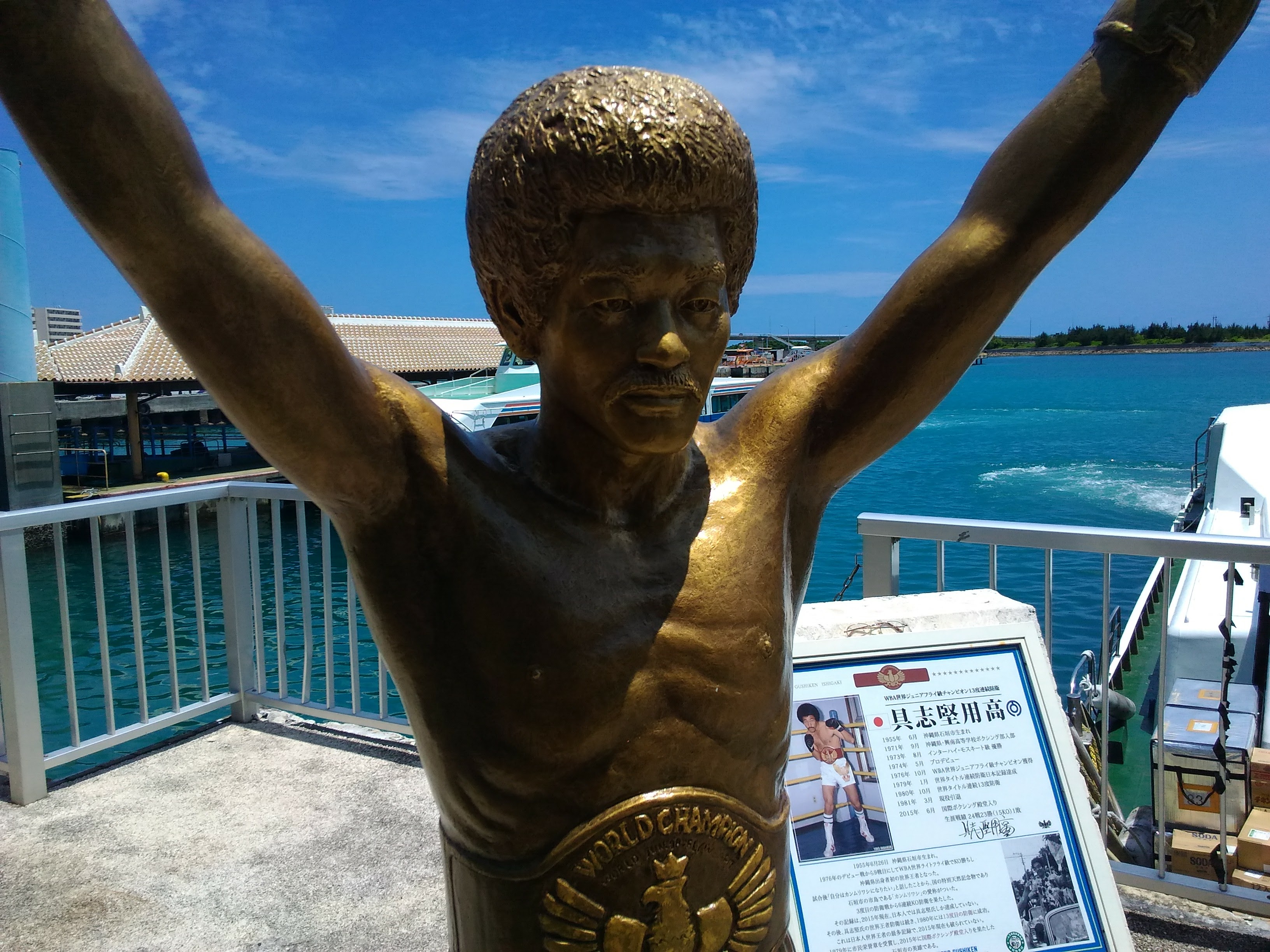



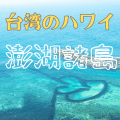


最近のコメント